-Back-
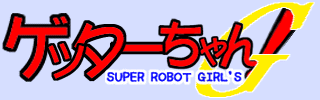 第2話 降臨、滅びの使者 「はぁ……」 買い物カートを押しながら、チヤカは憂鬱そうにスーパーの時計を見上げた。 彼女達の隣に恵の姿はない。ゲッターGの開発が大詰めを迎え、最終調整に入ってからの彼は連日の残業だ。恵の退社時間に付き合っていてはスーパーが閉まってしまうため、最近はこうしてチヤカ達だけで帰ることも多くなっていた。 四人で賑やかに夕飯の買い物をしていた頃が、遠い昔のようだ。 「あ」 ふと持ち上げたジャガイモが、両の手からぽろりとこぼれ落ちた。 どうやら、随分とぼうっとしていたらしい。 ハサミの指でそっと挟んでカゴへ入れ、そのまま賑わうレジへと並んだ。 (私にもし、指があったら……) そう考えた事は一度や二度ではなかった。いや、自身の設計図を見た瞬間から、そう思っていたのかもしれない。 自由に動く五本の指。チヤカがCPUを白熱させてようやく得た事を、ほんのわずかのルーチンで成し遂げてしまう憧れの存在。 恵の作ってくれた体だ。不満があろうはずがない。 けれど……けれど……。 (恵……っ) 小さな悩みが不満を呼んで、不満が不安をかき立てて、高まる不安がより悪い想像を生み出していく。恵を信じようと願うたび、嫌な想像は強く強くチヤカの胸を締め付ける。 (ちやちゃん……) 気が付けば心の中、イクルが不安そうにこちらを見つめていた。 ミクマは実験の後から黙ったまま、表層に現れようともしない。 (ちやちゃん、あたしの体と替わる?) 三人の中、唯一の五体を持つイクルが寂しそうに問いかけた。 (あたし、失敗ばっかりだし……ちやちゃんの方が、あたしの体も上手く使えるよ。きっと) そう言ってにっこりと笑う。今にも泣き出しそうな、崩れ落ちる寸前の悲しげな笑顔。 彼女の思いもきっと自分と同じなのだろう。 泣き出したいのは自分も同じだろうに。 それでも泣かず、チヤカを気遣う彼女の心に……微笑。 「……バカ言わないの」 涙を拭き、そう言い捨て、チヤカはレジにお金を払った。恵を抱くことも出来ない危険な体を、そそっかしいイクルなんかに預けられるはずがない。 おつりを受け取って財布に戻し。買った物を袋に詰めるため、近くの台へカートを押そうとして……そのカートが、ついと引っ張られた。 「ごめんなさいね。ちょっと、いいかしら?」 きれいな女性だ。けれど、メモリの中に彼女に関するログはない。 「失礼ですが……。どちらさま、ですか?」 声を掛けた女性を見上げ、チヤカは不審そうにそう問いかけるのだった。 三つ並んだ首の前に座り込み、恵はノートPCを無言で睨んでいた。 「なあ、マスター。ちょっと質問してもいいか?」 「んー?」 口を開いたタツキに気のない返事。どうやら考え事をしているらしく、誰が喋ったのかも気付いていないだろう。 「何で、イクル達はマスターを名前で呼ぶんだ? マスターも注意しないし」 「んー」 相変わらずの気のない相槌だけで、明確な回答はない。タツキは少し太めの眉をひそめると、何を思いついたのか意地悪な表情で言葉を紡いだ。 「だったらさ。オレ達もマスターの事……『恵』って呼んでもいいよな?」 「ん……っだあ!」 今度は返事も出来なかった。 「早乙女ぇ」 いつの間に現れたのか、大柄な白衣の男が恵の肩を乱暴に掴んだからだ。 例によって兜である。マッチ棒によりかかったマッチ箱のような体勢で、キーボードを打つ手を止めた恵に問いかける。 「残業もいいが、こいつらの話くらい、ちゃんと聞いてやれや」 「は、はぁ……。で、何?」 正面から問われたタツキは、言葉を続ける事が出来なかった。 優しい恵の背中越しに、昏い色をした輝きを見てしまったからだ。 「い、いや……」 光は問いかけの反復を許さない。 タツキの電脳に恐怖という感情が完全に焼き上がる半瞬前にその光は消え、いつもの人なつっこい糸目に戻る。 「こいつらがな、お前のこと『恵』って呼んでいいかだと」 な、と求められた同意に、タツキは恐る恐る賛同の意を示す。 「大方、イクル達の事が羨ましいんだろう。可愛いもんじゃねえか」 温厚に笑う兜に対する畏れはもうない。きっと恵も、二つ返事で許してくれるだろう。 「んー。ちょっとそれは、困るかな」 だが、恵はその提案をやんわりと断った。 「何でだよ! オレ達もイクル達も、同じじゃないか!」 あっさりとかぶっていた猫が落ち、普段の乱暴な喋りに戻る。 彼女達に良くて、どうして自分達はダメなのか。 試作品の彼女達にはない力を持っているのに。彼女達の持っている力でさえ、全て自分達の方が上回っているのに。 「あの子達は……特別だから」 そう言って、どこか照れたように笑う。 「フラれたなぁ。ま、コイツ以外にもいい男なんざ沢山いるって」 憮然としたままのタツキに兜はへらりと笑いかけ、ツインテールに分けられた赤い髪をわしわしとかき乱してやる。 「それ……主任の事ですか?」 茶化された恵も、珍しく茶化し返す。 「バカ言うなぃ。こんな若い子に手を出してみろ。カミさんに怒られっちまう」 「……は?」 その言葉に、恵は耳を疑った。 「主任、奥さんが居たんですか!?」 恵が入所した時、兜は独身と聞いたはずだ。その後に結婚したのなら、女子社員達の噂話にのぼらないはずがない。 「あー。いや、その、なんつーかな……」 何か不都合でもあるのか、兜はあさっての方向に視線をそらしたままブツブツと呟いている。いつもの堂々とした兜からは考えられないうろたえっぷりだ。 「……まあ、同類のお前ならいいか」 考えがまとまったのか、ポケットから小さなロケットを取り出してみせる。ぱちりと開けば、若い女性の写真が現れた。 「月姫だ。月の姫と書いて、ツクヒ。籍は入れてねえが、一応、俺のカミさんだ」 「……きれいな人じゃないですか」 恵よりは少し年上だろうか。肩までの淡くウェーブした栗色の髪に、小春日和に見上げたわた雲のような柔らかい笑みを浮かべた、小柄な女性だ。大上段の綺麗ではなく、自然体のきれい。可愛いという表現も少し違う、柔らかい仮名での表現がすんなりと合う、そんな雰囲気に包まれている。 十以上も離れた若い女の子と同棲している四十男。隠したい気持ちも分からないでもないが、若い恵からすればそこまで必死に隠さなくてもいいとも思う。別に不倫というワケでもないのだし。 「かれこれ、十五年ほどの付き合いになる……」 「……それは」 月姫を三十と見積もっても、中高生。兜は既に研究所員だったろう。朗らかに笑う写真の女性を見て、十五年前に手を出したのなら少し犯罪かも、と思い直した。 「お前でも気付かんか……」 そんな恵を見て何を思ったのか、兜が意味不明な発言をする。 「は? まさかこの人、主任より年上とか?」 考えを見透かされたような発言に少しだけ身を引く恵。どうみても若奥さんだが、もしかしたら違うのか。 「んなワケあるか。よく見ろ」 嘆息する兜にもう一度ロケットを目の前に見せられて。 「この人……まさか!」 恵は先程とは別の意味で、息を飲む。 スーパーの袋をドリルの腕に提げ、チヤカはようやく警戒を解いた。 「兜主任の奥様でしたか」 「ええ。うちの槍一郎が、いつもお世話になってます」 にこにこと笑うきれいなひと。ふっくらと仕上げられた厚手のセーターに動きやすい細身のジーンズを合わせたその格好は、どこから見ても普通の若奥様だ。 実直な兜主任にこんな若くてきれいなお嫁さんがいるなんて知らなかった。恵も主任は独身だと言っていたはずだから、帰ったら夕食のちょっとしたニュースになるだろう。 「それで、私達に何の御用ですの?」 歩きながら、そう問いかける。月姫はチヤカ達に用事があると言った。表だって面識のない自分達に、何の用があるというのか。 ……まさか。 「ああ、別に、恵さんとあなた達を引き離そうと思ってるわけじゃないから、安心して」 チヤカはその言葉に息を飲む。 まるで彼女の考えを読んだかのように月姫はそう言い、穏やかに笑っている。 『私たちもあなた達と同じだから、ちょっとお話してみたかったの』 次に聞こえた声は、人間の可聴域外からの声だった。 場所を近くの居酒屋に移し、兜の話は続いていた。 「もう十五年になるか……。何が起こったか、知ってるよな?」 兜の問いに、恵は烏龍茶を持ったまま首を縦に。 当時はまだ中学生だった恵でも覚えている。いや、アンドロイドの研究に関わるものとして忘れようはずもない。恵の人生の分岐点となったあの大事件。 「……第四次産業革命」 面白みのない言い方をすれば、アンドロイド元年という。 ある一地方都市の小さな研究所で最初のアンドロイドが起動したのが今から十五年前。中学生だった恵はその偉業に憧れ、いつか彼の地で研究をする事を決めたのだから。 「ツクヒは最初期の実験機でな……まあ、お前んとこの三人と似たようなもんだ」 十五年前、最初のアンドロイド起動に立ち会った男は、ビールを口にそう呟く。 ファーストアンドロイドの話は研究所の資料を確かめるまでもない。恵が忘れるはずはないし、受付のパンフレットにもしっかりと記されている。 その後継機は研究所作品の最も有名な名として、今でも脈々と受け継がれているのだから。 だが……。 「『マジンガー』の初期型って言えば!?」 その告白で、恵は全てを理解した。 兜が月姫を愛しつつ、研究所では存在をひた隠しにしていた理由。 兜がイクル達を必死で守ろうとする恵に力を貸してくれた理由。 そして恵を同類と呼んだ理由。 「知ってる顔だな、そりゃ」 ぬるまったビールを煽り、兜は一息。 アンドロイドを愛でる者はそう珍しくない。鑑賞用として、愛玩用として、中には恵のように家族のように想う者もいる。だから、月姫を妻と呼ぶ男がいても不思議ではない。 「当たり前じゃないですか……」 だが、違うのだ。そんなレベルではない。 兜月姫。 世界最初のアンドロイド。 十三年前の国際条約が決まる以前の存在。 「だって、ファーストマジンガーは……」 ツクヒの。 兜月姫の正体は……。 「さっきあれから電話があってな。今、お前んとこの連中といるそうだ」 ビール越しのその告白に、居酒屋のテーブルががたんと鳴った。 コトコトと、深底の鍋が湯気を立てている。 「ぐんじへいき、ですか」 全く実感の伴わない単語を、チヤカは口に出してみた。 「すごいでしょう。もう、私しか残っていないのよ?」 えへへ、と得意げに笑う月姫はどう見ても人間だ。百歩譲ってアンドロイドだとしても、ごく普通の家庭用アンドロイドとの違いが分からない。 「寂しくないんですか? たった一人で」 「そりゃ、ちょっとは寂しいけど……だんな様がいるからねぇ」 研究所にほど近い兜邸の、広いキッチン。 沸き立つ鍋にショウガを削り入れながら、にこにこと笑うきれいな女性。 やっぱりその辺の若奥さんだ。軍事兵器という単語は、どうしても一致しない。 「それにしてもチヤカちゃん。上手ねぇ」 チヤカの腕は相変わらずのドリルとハサミだ。常識では不可能に見えるジャガイモの皮むきすら、包丁で器用にこなしてみせる。 「慣れてますから」 答える声には小さなトゲが秘められていた。 こんな見かけだから、出かけた先で褒められることはそれなりにある。けれど、それは全てプログラムした者への賞賛だ。まあ、それは当然と言える。チヤカ自身が導き出した技法だなどとは、普通誰も思わない。 恵が褒められるのだから悪い気はしないが、どこかが引っかかる。 「たくさんたくさん、練習したのねぇ」 「……へっ!?」 ぽろりと、チヤカの手から人参がこぼれ落ちた。 「あら、私、変なこと言ったかしら? ごめんなさい」 キッチンの床をコロコロと転がる人参を拾い上げ、そっと手の中に戻してやる。 「……出来合いや、恵が組んだプログラムだとは思わないんですか?」 「別の人が作ったプログラムは、こんなに優しく走らないもの」 そう言って、チヤカがむき終わった人参を取り上げた。所々角のある、月姫の人参から見ればはるかに不格好なむき身の人参。 イクル並みの不器用ならまだしも、普通に剥いた人参とは比べるべくもない。 「大好きな人のために、きっとものすごく頑張ったのね」 人参を置き、セーターの袖でチヤカの涙を拭ってやる。 「その人は、喜んでくれた?」 震える肩を抱き、胸元にそっと導けば…… 「うわああああああん!」 暖かな匂いの漂うキッチンに、緊張の糸が切れた少女の泣き声が響き渡る。 「なっ!」 立ち上がり掛けた恵を、兜は大きな手で押しとどめた。 「そんなに大声出すんじゃねえよ」 ひょいと掴んだだけに見えるのに、どれだけ力を入れてもぴくりとも動かない。学生時代は柔道だかレスリングだかをやっていたという兜だ。格闘技に疎い恵には及びも付かない技のひとつも使っているのだろう。 「だって主任! イクル達とファースト……っ」 そこまで言って、恵は今度こそ言葉を失った。兜に腕をねじり上げられ、呼吸まで危なくなっている。 「だから、今の月姫は軍事用じゃないんだって」 先程、自分で軍事用アンドロイドと言ったばかりではないか。 人と同じ姿で、人と同じ笑顔を浮かべたまま、人ならぬ力で人を殺すもの。あまりに非人道的なデビューを飾ったその存在は、生まれてからたった二年で国際的な全廃条約が可決されるほどだった。 以来、世界に戦争は消えなかったが、軍事用アンドロイドだけは現れていない。ルールなど存在しない局地戦やテロですら、だ。 「今のあいつは、俺が作った汎用機のボディを使ってるよ。それに、オリジナルのままでケンカされちゃ、俺の命が危ねえ」 「……そう、っすね」 耳元で静かにそう言われ、恵はようやく息を吐く。 「俺の嫁さんは賢いよ。ただちょっと、おおっぴらに自慢できんだけでね」 兜は静かにそう言い、自分のビールをくいと飲み干すのだった。 |
< Before Story / Next Story >
-Back-